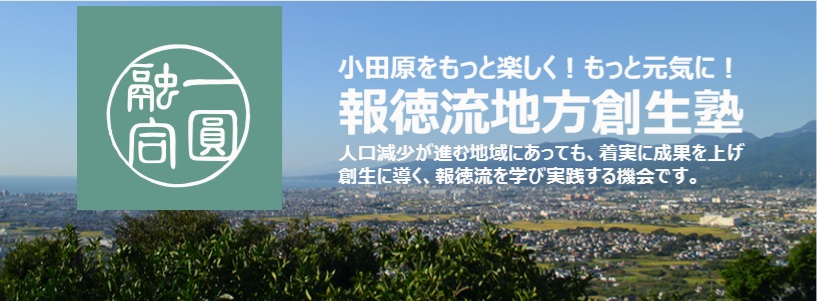事業趣旨
人・もの・お金が地域に循環する、持続的発展が可能な社会をめざして。
情報や流通などの発達により、世界においては国境や言葉や文化の壁を超えたグローバルな社会基準が形成され、日本の大企業もこれに負けじと活躍をしていますが、日本国内、特に中小企業や農林水産業においては少子高齢化社会のなか、人口減少や大規模チェーン店等で販売される安価な海外商品との過当競争の中で、さまざまな問題が山積しています。そして省みればこの間、物質的には非常に豊かな社会になったとはいえ、精神的には元々日本人が持っていた良さや伝統は薄れ、「自由」という言葉とは裏腹に「無責任」が横行し、どんどんと人間関係が希薄化し、日本の社会・地域コミュニティーが崩壊し、文化の継承が途絶えているように思えます。
この時代を生きる私たちには、今後ますます消費の減少や労働人口の減少が顕著になっていく未来を見据えて、右肩上がり・経済一辺倒の考え方から、この時代に対応でき得る新しい心豊かな社会づくりへの発想・業態の転換が求められています。
現在、日本各地でも新しい時代への取り組みとして、環境問題・教育・福祉を含んで「まちづくり会社」「NPO法人」などを筆頭に、行政や民間主導でのさまざまな取り組みが行われており、ここ小田原においても行政における無尽蔵プロジェクトや民間団体それぞれが主体となって、多くの活動が行われております。
「報徳二宮神社 まちづくり推譲事業」は、こうした活動とほぼ趣旨を同じくするものではありますが、その考え方と手法は当社の御祭神である、二宮尊徳翁が江戸時代に実践した「報徳思想」「報徳仕法」であり、その精神と手法に則り、今後小田原を中心とした神奈川県西湘地域に、今まで以上にヒト・モノ・カネが循環し、未来の子供たちの世代においても持続的発展を遂げられるように、「経済と道徳一元」の教えのもと、今「失われつつあるもの」や「輝きを失いかけているもの」「現状困っているもの」に焦点をあて、これらを再構築していくことを目的とし、この事業を報徳二宮神社の「まちづくり推譲事業」として位置づけ、報徳博物館での思想の研究・普及活動と並行しながら、現代における報徳の実践活動を通して、実践の学問として報徳の教えを次世代に継承していきたいと考え行うものであります。
平成22年9月 報徳二宮神社 宮司 草山 明久
報徳二宮神社まちづくり推譲事業について(1002.4KB)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です
◆現在、実践しているまちづくり推譲事業
小田原柑橘倶楽部
平成22年(2010)より、御祭神二宮尊徳翁がかつて実践した「報徳思想」「報徳仕法」をお手本としながら地域活性化を目的とした「片浦みかんプロジェクト」を開始。現在はその幅を更に広げ2015年には地元14社による出資にて(株)小田原柑橘倶楽部を設立し耕作放棄地を開墾。現在約600本のレモンを育てているほか、地域内における農商工連携を推進し、農家と商工業者をつなぐエンジン役としての役割を果たしながら、6次産業の推進など「人・もの・お金」を地域でまわす取り組みを進めています。
*小田原柑橘倶楽部の詳細はこちらから
【小田原柑橘倶楽部の受賞歴】
平成23年度「食と地域の『絆』づくり」の優良事業 農林水産省
箱根口ガレージ報徳広場
小田原市南町の観光交流促進と3世代が交流する地域コミュニティ形成事業
報徳二宮神社「まちづくり推譲事業」の第2プロジェクトとして令和3年(2021)より行う活動。道徳と経済を両輪として心豊かに暮らせる地域社会を目指したご祭神の思想と仕法に則り、経済的にも自立をした人たちが自発的に3世代が交流できる場づくりを目指して活動するプロジェクト。人口減少や大規模チェーン店などにより個人商店が減少する同地区において、昼間は南町周辺の観光交流人口の促進による地域経済の活性化を目的とした飲食事業などを展開し観光客を誘致。夕方からは近隣住民が3世代交流できる拠点づくりを目指して活動しています。新型コロナウィルスがまん延した中での開業となりましたが、現在多くの協力者と共に活動の輪を広げています。
*箱根口ガレージ報徳広場のホームページはこちら
報徳二宮神社では、報徳博物館と共に学びの場を提供しています。